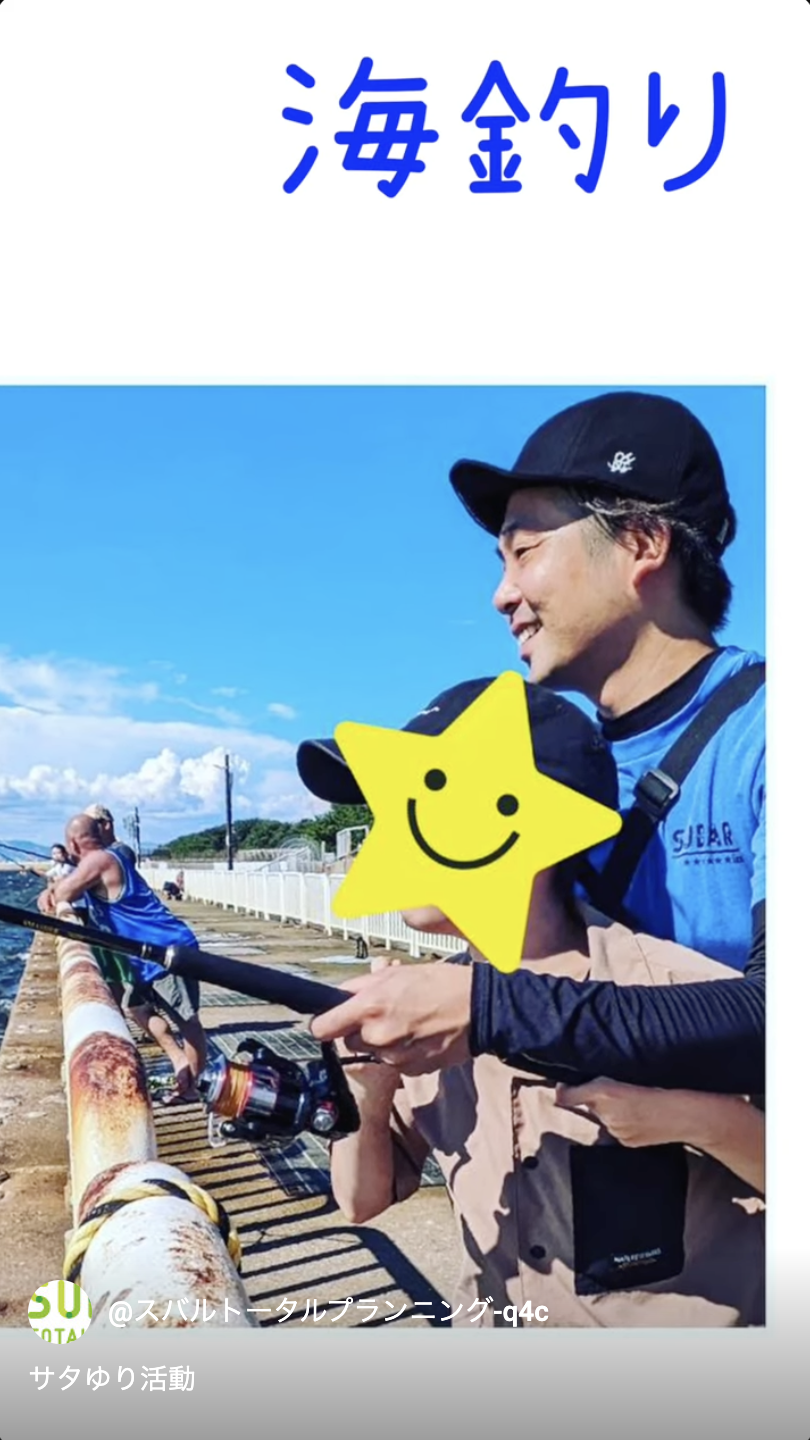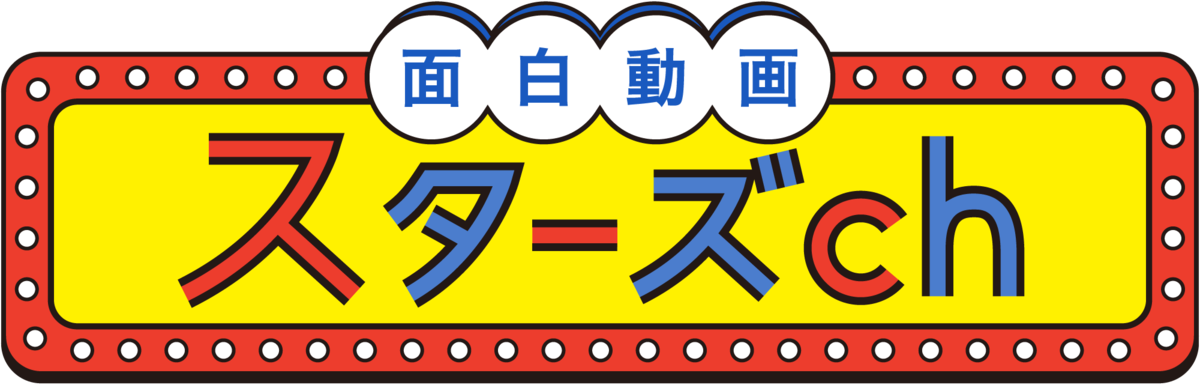あれから季節はめぐり、スバルの“極秘プロジェクト”だった「320」は、少しずつその全貌を現しはじめました。
名前は──「ムカイノベース」。
向野のまちに、福祉と地域が交差する、新しい拠点が誕生しようとしています。
いったい、どんな想いでこの施設は構想され、どんな未来を描いているのか?
今回は、ムカイノベースを企画・推進してきたキーパーソンに、記者がじっくりお話をうかがいました。
「福祉の枠を超えたい」「地域とつながる拠点にしたい」──そんな熱い想いが詰まった、誕生秘話をどうぞ!

今日は、いよいよ動き出す「ムカイノベース」について、皆さんにもより深く知ってもらえるよう、代表の佐藤さんにお話を伺います。 |
今日は、いよいよ動き出す「ムカイノベース」について、皆さんにもより深く知ってもらえるよう、代表の佐藤さんにお話を伺います。
まず、名前から伺いたいのですが、「ムカイノベース」とはどのような意味が込められているのですか?
佐藤:
はい。「ムカイノ」は、施設が立地する羽曳野市の向野(むかいの)という地名に由来しています。
地域に根差した場所をつくりたいという想いから、この名前を選びました。
「ベース」は英語で“拠点”や“基地”という意味です。
つまり、ムカイノベースは、“地域と人がつながり、新しい価値が生まれる拠点”になることを目指しています。
障がいのある方々が地域と関わりながら、自分らしく生き、働き、輝ける場所。
ただの福祉施設ではなく、地域に開かれた共生の場をつくる、という構想を名前に込めました。
とても素敵な意味ですね。では、そもそもなぜ、今このタイミングでムカイノベースを立ち上げようと思ったのですか?
佐藤:
それには、スバル全体としての問い直しがありました。
「私たちは、地域で必要な企業なのか?」
「“利用者本位”とは何かを考え続ける?それをちゃんと行動にできているのか?」
この問いを、もう一度ゼロから見つめ直したのが出発点です。
私自身が大切にしているのは、障がいのある方が、仕事や活動を通じて、地域の方々とつながり、必要な存在になることです。
そして、それが「生きがい」や「働きがい」につながる。
福祉サービスを“守る場”としてだけでなく、“つながりを生む場”として再定義したかったんです。
ムカイノベースはその象徴的な場所であり、福祉の枠を超えて、地域の未来を共につくるチャレンジだと思っています。
全国的にも、福祉と地域をつなげるような施設が増えている印象がありますが、ムカイノベースは他と何が違うのでしょうか?
佐藤:
確かに最近は、福祉×カフェや福祉×農業といった事業が増えています。特に、就労継続支援B型では多く見られます。
ですが、ムカイノベースは生活介護事業として、「支援がたくさん必要な方も社会と関われる」ことに挑戦します。
たとえば、カフェでは接客したり、調理ができる方は限られるかもしれません。
でも、野菜の袋詰め、紙袋のデザイン、料理の盛り付け補助、テーブル拭き――
こういったバックヤードの仕事もすべて、「社会と接続している」と私は考えています。
大事なのは、「何をするか」ではなく、「どう関わるか」。
自分の得意やペースに合わせて、社会とつながる形を見つけていくことが、福祉の本質だと思っています。
「今のお話から、施設をつくることそのものが“福祉の再定義”でもあるように感じました。では、その想いを、どんな形で日々の活動として体現していくのでしょうか?」

佐藤:
ムカイノベースには、3つの大きな機能があります。
① 生活介護事業(定員20名):事業所名「320lab.」
畑での農作業やアート活動、紙袋や商品ラベルのデザインなど、
ご利用者が自分のペースで取り組みながら、「価値を生み出す喜び」を実感できる場所です。
ここでは“仕事”としての手ごたえを感じてもらうことを大事にしています。
② カフェ・ショップ「日々のお台所」
地元の旬野菜を使ったランチを提供したり、
320lab.で作られた商品やアートを販売する拠点です。
ここは、地域の人が日常的に訪れる“つながりの玄関口”。
福祉のことを知らない人にも、気軽に関わる場を目指しています。
③ フリースペース「色どりの間(あいだ)」
こちらは多世代が集まり、ワークショップやイベントが開かれる場です。
貸しスペースとしても柔軟に使ってもらい、「交流を生む間(あいだ)」になればと思っています。
一方で、既存で運営されている生活介護事業「ライフサポートぐっぴい」との違いに、戸惑いを感じているスタッフもいるようです。その点についてはいかがでしょうか?
佐藤:
それもよくあるご意見だと思います。ぐっぴいと320lab.は、同じ生活介護事業ですが、アプローチとフィールドが違います。
ぐっぴいでは、主に安心・安定した支援の中で、日々の暮らしを大切にする取り組みをしてきました。
一方で、320lab.では、日常の延長線上に“社会との関わり”をつくることを意識しています。
「社会と接続する」というのは、商品にラベルを貼ること、畑作業に関わること、地域のイベントに顔を出すこと、そのすべてが接続だと思っています。
これまでのぐっぴいでは、確かにそうした機会が少なかったかもしれません。
でも、ムカイノベースという“新しい場”ができることで、ぐっぴいのご利用者にも新しいチャンスが広がっていくと信じています。
“社会と接続する”という言葉が、単に「外で働く」ことや「表に立つこと」だけではないというお話に、はっとさせられました。
日々のささやかな関わりや役割の中にこそ、確かなつながりがある──そう思うと、福祉の本質がより身近に感じられますね。
ぐっぴいとムカイノベースは別の建物でも、同じビジョンに向かっているんですね。
佐藤:
はい、我社の中期ビジョン「地域を楽しむ、地域と楽しむ」です。
「どこにいるか」よりも、「どう関わるか」が大切です。
そして、施設は完成しますが、ムカイノベースの本当の意味での完成はこれからです。
スタッフやご利用者、ご家族、地域の人たちと一緒に“育てていく拠点”にしていきたいと思っています。
「これから関わっていくスタッフ、そして地域の皆さんに向けて、どんな思いを届けたいですか?」
佐藤:
これは、一つのチャレンジです。
正直、まだ正解はありません。でも、だからこそ、一人ひとりのアイデアや気づきがとても大切なんです。
ご利用者も、スタッフも、それぞれの関わり方で“社会とつながる”ことができる。
それを信じて、共につくっていきましょう。
そして何より、このプロジェクトを楽しんでほしい。
「うまくいくかどうか」ではなく、「誰と、何を、どう作るか」。
その過程こそが、地域にとっても、スバルにとっても、価値のある時間になると信じています。
この施設を支えるのは、我々だけではありません。
地域の方々、関わるすべての人の「関心」と「共感」が、ムカイノベースを育てる力になります。
編集後記(記者より)
このインタビューを通して、ムカイノベースは“完成された施設”ではなく、 「みんなで育てていく生きた拠点」だということが強く伝わってきました。
スタッフ一人ひとりが、自分の仕事の先に「社会との接点」を見出しながら、共に未来を創っていく場――それがムカイノベースなのだと感じました。
カフェ<日々のお台所>
令和7年7月10日(木)プレオープン(予定)
8月1日(木)グランドオープン!
営業日:木・金・土 11:00~16:00
フリースペース完備
住所:大阪府羽曳野市向野1丁目46番1
お問合せ:info@subaru-tp.com